高島市歴史散歩特集
今まで広報誌に掲載されてきた歴史散歩を一挙公開
2005年(平成17年)1月1日に、高島市が発足した時から広報誌に掲載されてきた歴史散歩。
2025年(令和7年)6月1日の中江藤樹・たかしまミュージアムの開館に際して、今まで続いてきた歴史散歩を一挙公開いたします。
高島市文化財保存活用地域計画では、地域の多種多様な文化財を歴史文化の特徴に基づき、一定のまとまりとして扱うため、「5つのストーリー」を設定しています。
今まで掲載されてきた歴史散歩を、高島の歴史文化を表す「5つのストーリー」とサイドストーリーで分類しています。
ごゆっくりご覧ください。
このストーリーに含まれる歴史散歩
| 歴史散歩 タイトル | 掲載広報誌 |
|---|---|
| 継体天皇と高島市 | 平成17年4月 |
| 神話と歴史の息づく集落ー拝戸ー | 平成18年3月 |
| 音羽古墳公園 | 平成18年11月 |
| 継体大王にまつわる伝承とその遺跡 | 平成18年12月 |
| 高島市の新しい指定文化財 | 平成19年2月 |
| 継体天皇を支えた古代豪族 三尾氏族の石室発見! | 平成19年12月 |
| 継体天皇伝承地「えな塚」 | 平成20年4月 |
| 古代末から中世までの村と暮らしの一端~平成19年度堀川遺跡発掘調査成果から~ | 平成20年6月 |
| 安曇川田中古墳群 | 平成20年10月 |
| 打下古墳の発見 | 平成20年11月 |
| 沿道沿いに栄えた物流拠点「弘部野遺跡」 | 平成21年7月 |
| 市内最大規模の古墳群~北牧野古墳群・西牧野古墳群~ | 平成21年11月 |
| 安曇川町 南市東・下五反田遺跡 | 平成22年8月 |
| 継体天皇千五百年の謎~継体の生誕地・高島から探る~ | 平成22年9月 |
| 全国を巡回する安曇川町田中出土の馬具 | 平成23年7月 |
| 天神畑・上御殿遺跡とは | 平成24年1月 |
| 黄泉の国への訪問話~新旭町出土 蛤入りの土器~ | 平成24年6月 |
| 生徒たちが発見した湖西中学校保管の土器展示 | 平成25年1月 |
| 発掘された地震跡 | 平成25年8月 |
| 東京国立博物館と馬塚古墳 | 平成26年2月 |
| 高島歴史民俗資料館と周辺遺跡群 | 平成26年3月 |
| 古代製鉄~北牧野くちなし谷炭窯遺跡~ | 平成26年8月 |
| 高島市の埋蔵文化財 | 平成26年11月 |
| 古の高島を語る 二つの王塚 | 平成27年1月 |
| 古代の装身具ー発掘された宝石たちー | 平成27年9月 |
| 下花貝遺跡 発掘調査中! | 平成28年8月 |
| 下花貝遺跡の最新情報 | 平成28年11月 |
| 古墳時代の高島 | 平成29年10月 |
| みて・ふれて・かんじて古墳時代の高島 | 平成29年11月 |
| 北牧野古墳群 | 令和元年12月 |
| 琵琶湖・淀川水系を利用して運ばれた家形石棺 | 令和2年6月 |
| マキノ地域の古代製鉄跡とその足跡 | 令和2年10月 |
| 京都橘大学考古学研究室による拝戸古墳群の測量調査 | 令和3年2月 |
| 高島歴史民俗資料館 見て歩き | 令和5年2月 |
| マキノ町蛭口宮遺跡出土の「和同開珎」 | 令和5年4月 |
| 赤色顔料とL字状石杵 | 令和5年9月 |
| 高島の古代遺跡 その1 | 令和6年6月 |
| 県下最大級の高地性集落 | 令和6年8月 |
| 妙見山古墳群からみる古代のアクセサリー | 令和7年1月 |
このストーリーに含まれる歴史散歩
| 歴史散歩 タイトル | 掲載広報誌 |
|---|---|
| 高島市を通る街道と道標 | 平成17年3月 |
| 鵜川四十八体仏 | 平成17年6月 |
| 山中の関所跡 | 平成17年8月 |
| 北船木の若宮神社 | 平成17年9月 |
| 安曇川の歴史を伝える橋-安曇川大橋・本庄橋・常安橋ー | 平成17年12月 |
| 後一条天皇の伝承が残る庭園跡ー朽木村井地区・池の沢遺跡ー | 平成18年1月 |
| 長期間続いた集落跡~今津町弘川地区~ | 平成18年4月 |
| 湖西の人々の生活を支えた江若鉄道 | 平成18年6月 |
| 蒸気船時代の賑わいと桟橋の成立 | 平成18年7月 |
| 踊り歌の成立と高島音頭 | 平成18年8月 |
| 朽木谷の木地屋と道具 | 平成19年3月 |
| 16年ぶりに再現!三重生「うしの祭り」 | 平成19年4月 |
| 「安曇」の地名が語るもの | 平成20年5月 |
| 江戸時代に全国ブランドの「朽木盆!」 | 平成20年12月 |
| 「鯖街道」の最短ルート~根来峠~ | 平成21年1月 |
| 江戸時代に全国ブランド パート2 「高島硯」 | 平成21年2月 |
| 岩神(朽木岩瀬)の将軍御所 | 平成21年4月 |
| 剣熊関の役割 | 平成21年5月 |
| 全国的に類例のない謎のダム遺構「岩神堰堤遺跡」 | 平成21年8月 |
| 『民具』~くらしと共に歩んだ道具たち~ | 平成23年1月 |
| 太陽信仰の聖地に造られた 日置前の遺跡 | 平成23年3月 |
| 自然とともに生きる | 平成23年8月 |
| 「高島音頭」を伝える新資料発見! | 平成23年9月 |
| 六種の木 | 平成23年12月 |
| 近江と若狭を結ぶ粟柄峠 | 平成24年2月 |
| 新名勝指定!朽木池の沢庭園 | 平成24年3月 |
| 朽木・宮ノ前の春祭り | 平成24年5月 |
| 今に残る江若鉄道の足跡 | 平成24年7月 |
| 阿弥陀山と太山寺 | 平成24年8月 |
| 南市と安原仁兵衛 | 平成24年10月 |
| 今に残る安曇川扇状地の条里制 | 平成24年11月 |
| 百瀬川隧道の成立 | 平成25年3月 |
| 奈良の都へ続く「小川津」 | 平成25年6月 |
| 寺の関係者で造られた名園 | 平成25年7月 |
| 県内唯一の「石敢当」 | 平成25年11月 |
| 高島の古代寺院 | 平成25年12月 |
| 追加指定の文化財 朽木の木地屋の製品 | 平成26年4月 |
| 新指定の文化財 高島硯の製造道具 | 平成26年9月 |
| 街道沿いの常夜灯 | 平成26年10月 |
| 北牧野の雪積み場 | 平成27年2月 |
| 「王の舞」の系統を継ぐ 安曇川の春祭り | 平成27年4月 |
| 追加指定の文化財 神と仏の世界~椋川の懸仏群~ | 平成27年5月 |
| 江戸時代の全国ブランド~朽木産の天然仕上げ砥石~ | 平成28年1月 |
| 祭りの影の主役お守りとしても大切にされてきた餅 | 平成28年2月 |
| 高島市の春を告げる 川上祭 | 平成28年4月 |
| 江戸時代の焼物 今津町日置前焼 | 平成28年6月 |
| 北国街道と川原市宿 | 平成28年10月 |
| 古代から中世へ 今津弘川の遺跡群 | 平成28年12月 |
| 高島のヴォーリズ建築 今津ヴォーリズ資料館 | 平成29年1月 |
| 幕末の北国海道 | 平成29年3月 |
| 古代から近代まで続いた「筏流し」 | 平成29年5月 |
| 朽木谷を経由した若狭街道~針畑越と朽木街道~ | 平成29年6月 |
| 今津町弘川の遺跡群と地鎮祭 | 平成29年7月 |
| 峠を越えた筏と魚の話 | 平成29年8月 |
| 大般若経が運ばれた古道・近江坂 | 平成29年12月 |
| 中世末期の貴重な武家庭園 国名勝 旧秀隣寺庭園 | 平成30年1月 |
| 高島トレイルの終点「丹波越」 | 平成30年3月 |
| 蓮如上人御影道中 | 平成30年4月 |
| 金毘羅参りの楽しみ | 平成30年6月 |
| 中世に活躍した南市商人 | 平成31年2月 |
| 湖西線沿線の文化財の紹介 | 平成31年4月 |
| 今津宿と今津浦 | 令和元年6月 |
| 都市経済を支えた朽木材 | 令和元年9月 |
| 高島のくらしと民具 | 令和元年10月 |
| 市内の登録有形文化財 | 令和2年2月 |
| 天台宗寺院 長法寺跡 | 令和2年8月 |
| 高島市の聖徳太子信仰 | 令和3年1月 |
| 湖北と高島を結んだ道 | 令和3年4月 |
| 鴨遺跡出土の荷札木簡 | 令和3年7月 |
| 文学作品にみる「あらち」 | 令和4年3月 |
| 入部谷越え | 令和4年8月 |
| 玉泉寺の石仏群 | 令和4年9月 |
| 地質図からみる高島とその歴史 | 令和5年1月 |
| 回されたお触れ書き | 令和5年10月 |
| 紫式部が見た「三尾が崎」 | 令和6年1月 |
| 待ち望まれた湖西線 | 令和6年7月 |
| 高島の古代遺跡 その2 | 令和6年11月 |
このストーリーに含まれる歴史散歩
| 歴史散歩 タイトル | 掲載広報誌 |
|---|---|
| 朽木陣屋跡 | 平成17年7月 |
| 高島に築かれた織田一族の城ー大溝城ー | 平成17年10月 |
| 田中城跡と田中吉政 | 平成18年9月 |
| 四海太平記と朽木植綱 | 平成19年7月 |
| 「四海太平記」シリーズ2 朽木城の軍勢強し! | 平成19年8月 |
| 「四海太平記」シリーズ3 高島勢が協力し、大軍を撃退! | 平成19年9月 |
| 関ヶ原の戦い~朽木元網の決断~ | 平成20年8月 |
| 近江大溝藩と若狭小浜藩 | 平成21年10月 |
| 大溝城~その過去・現在・未来~ | 平成22年2月 |
| 全国的に貴重な鎌倉~戦国時代の文書群 朽木文書 | 平成22年3月 |
| 戦国期拠点城郭 国史跡 清水山城館跡 | 平成22年4月 |
| 磯野員昌と新庄城 | 平成22年6月 |
| 海津衆田屋氏と江北浅井氏 | 平成22年11月 |
| 大溝城フォーラム2 大溝城の歴史的変遷を考える | 平成23年2月 |
| 織田信長、大船で高島を攻める | 平成23年10月 |
| 清水山城と城下 | 平成23年11月 |
| 武芸の訓練の場~犬ノ馬場~ | 平成24年4月 |
| 饗庭三坊と城 | 平成24年12月 |
| 朽木陣屋の御殿に付属する土蔵・台所・馬屋 | 平成25年4月 |
| 大溝城と水口岡山城 | 平成27年11月 |
| 大溝城遺跡の発掘調査 | 平成29年4月 |
| 朽木氏の威厳を伝える旧興聖寺跡 | 平成30年7月 |
| 高島各地にある大名飛地領 | 平成30年8月 |
| 大溝藩と分部氏 | 平成30年10月 |
| キリシタンの奥方 | 平成30年11月 |
| 高島の明治維新 | 平成30年12月 |
| 日爪の城 | 令和元年11月 |
| 記録に登場する田中城 | 令和2年3月 |
| 高島市無形民俗文化財竹馬祭 | 令和2年4月 |
| 田中氏の居館 | 令和2年5月 |
| 疫病との闘い | 令和2年7月 |
| 近藤重蔵の業績とその顕彰 | 令和3年6月 |
| 永田城跡と法界地蔵 | 令和3年12月 |
| 琵琶湖の渇水と湖底遺跡 | 令和4年1月 |
| 阿弥陀寺と杉谷善住坊 | 令和4年12月 |
| 重蔵と瑞雪禅院 | 令和5年6月 |
| 大溝城から大溝陣屋へ | 令和5年11月 |
| コンピューターグラフィックスで再現 大溝城 | 令和6年2月 |
このストーリーに含まれる歴史散歩
| 歴史散歩 タイトル | 掲載広報誌 |
|---|---|
| 近江聖人の教えを伝える史跡~藤樹書院~ | 平成18年5月 |
| 藤樹文庫の開設 | 平成20年1月 |
| 中江藤樹先生と大溝 | 平成20年7月 |
| 中江藤樹の息子 常省 | 平成28年7月 |
| 渋沢栄一と藤樹神社 | 令和2年9月 |
| 中江藤樹とその教えを受け継ぐ人々―渋沢栄一・熊沢蕃山― | 令和3年10月 |
| 国史跡「藤樹書院跡」指定100年のあゆみ | 令和3年11月 |
| 創立100年を迎えた藤樹神社~創立に関わった偉人たち~ | 令和4年5月 |
| 「庚申さん」への信仰 | 令和4年6月 |
| 中江藤樹と高島の学びの系譜 | 令和4年11月 |
| 中江藤樹の志とともに | 令和5年5月 |
| 加藤盛一と高島 | 令和5年7月 |
| 藤樹研究の一大拠点「小川寮」 | 令和5年12月 |
| よみがえった遺愛の藤 | 令和6年5月 |
| 富岡鉄斎と高島のつながり | 令和6年10月 |
このストーリーに含まれる歴史散歩
| 歴史散歩 タイトル | 掲載広報誌 |
|---|---|
| 高島郡の成立 | 平成17年1月 |
| 高島市の式内社 | 平成17年2月 |
| 高島市・春の祭礼めぐり | 平成19年5月 |
| 大溝城下町を歩く | 平成19年11月 |
| 守り続けられてきた風景~これからの重要文化的景観~ | 平成20年9月 |
| 秋の収穫に使用した民具 | 平成21年9月 |
| 安曇川水系固有のシコブチ信仰 | 平成21年12月 |
| 古文書の語る海津の石垣~マキノ古文書クラブの活動から~ | 平成22年7月 |
| 『針江・霜降の水辺景観』 重要文化的景観に選定 | 平成22年10月 |
| シシ垣 | 平成22年12月 |
| 中世の社殿 | 平成23年4月 |
| 麗しの嶽山 | 平成23年5月 |
| 驚きの高島シシ垣、今昔物語 | 平成24年9月 |
| 夏の思い出ウォーク 近江高島から北小松 | 平成25年9月 |
| ー城と城下ー 大溝を歩く | 平成25年10月 |
| 白鬚神社の湖中大鳥居 | 平成26年1月 |
| 大溝を歩くー総門ー | 平成26年7月 |
| 「大溝の水辺景観」国の重要文化的景観に | 平成26年12月 |
| 裏の湖(うみ)~乙女ケ池 | 平成27年6月 |
| 日本遺産 初の認定「琵琶湖とその水辺景観」と朽木小川の「思子淵神社」 | 平成27年7月 |
| 琵琶湖八景の誕生 | 平成27年12月 |
| 安曇川がつなぐストーリー | 平成28年5月 |
| 海津浦に着いた丸子船 | 平成29年2月 |
| 400年の伝統 大溝祭 | 平成30年5月 |
| 大溝祭 曳山の装飾 | 平成31年1月 |
| 白鬚神社の文化財建造物 | 令和元年7月 |
| 文化財建造物の建築・修理記録 | 令和3年8月 |
| 大善寺の変遷 | 令和4年4月 |
| 白髭神社の保存修理 | 令和7年3月 |
このストーリーに含まれる歴史散歩
| 歴史散歩 タイトル | 掲載広報誌 |
|---|---|
| 高島市の義経伝承 | 平成17年5月 |
| 日本舞踊や歌舞伎でも知られる伝説の女性ー海津のお金ー | 平成17年11月 |
| 100万年前のゾウの足跡化石~安曇川町上古賀地区~ | 平成18年2月 |
| 明治時代の小学校 | 平成18年10月 |
| 正月の儀礼と行事 | 平成19年1月 |
| 高島市・芭蕉の句碑めぐり | 平成19年6月 |
| 椋川の学校 今・昔 | 平成19年10月 |
| スキー場の成立 | 平成20年2月 |
| 琵琶湖哀歌の誕生と四高桜 | 平成20年3月 |
| ひな祭りと「古雛展」 | 平成21年3月 |
| 「鴻溝城裡謫遷客」の詩碑 | 平成21年6月 |
| 資料館見て歩き チョロリ・ロクロ・人形 | 平成22年1月 |
| 室町時代の多彩な茶道具が出土 西万木遺跡の発掘調査 | 平成22年5月 |
| 高島の地震の史料 | 平成23年6月 |
| 資料館で郷土学習 | 平成25年2月 |
| 遺跡を記録する | 平成25年5月 |
| 描かれた冥土の王たち | 平成26年5月 |
| 湖底遺跡からみる自然の猛威 | 平成26年6月 |
| 琵琶湖治水の先覚者 藤本太郎兵衛 親子三代 | 平成27年3月 |
| 船木の飛行場 | 平成27年8月 |
| 世界遺産の礎を築いた高島商人ー小野権右衛門勝礼と橋野鉄鉱山・高炉跡ー | 平成27年10月 |
| 記憶の中の軍票 | 平成28年3月 |
| 歌い継がれて100年 琵琶湖周航の歌 | 平成28年9月 |
| メタセコイア並木の誕生 | 平成29年9月 |
| 県の文化財に指定された波爾布神社 | 平成30年2月 |
| 養蚕と製糸工場 | 平成30年9月 |
| 慶成館の成り立ち | 平成31年3月 |
| 新元号の発表 | 令和元年5月 |
| 市指定文化財の修理~絵画~「釈迦十六善神像」 | 令和元年8月 |
| 高島市ゆかりの文人たち | 令和2年1月 |
| 安曇川町の誕生と庁舎の建設 | 令和2年11月 |
| 琵琶湖博物館で展示中の饗庭野断層 | 令和2年12月 |
| 大溝藩の藩校 | 令和3年3月 |
| 朽木出身の偉人ー池田白鴎・高島玄俊ー | 令和3年5月 |
| 上弘部分校の役割 | 令和3年9月 |
| 大雪災害の記録 | 令和4年2月 |
| 饗庭野と演習場 | 令和4年7月 |
| 高島の仏教絵画とその世界 | 令和4年10月 |
| 旧制県立今津中学校の開校 | 令和5年3月 |
| 出征した梵鐘と代用の鳴らない鐘 | 令和5年8月 |
| 料館の歩みとこれから | 令和6年3月 |
| 絅斎書院100周年 | 令和6年4月 |
| ペリー来航と関藍梁 | 令和6年9月 |
| 『高島郡誌』記載の旧跡 | 令和6年12月 |
| 源氏物語と江戸時代の書籍出版 | 令和7年2月 |
| 新施設の名称が決まりました!! | 令和7年4月 |
歴史散歩一覧表(令和7年4月号まで) (PDFファイル: 335.5KB)
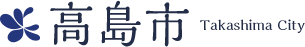











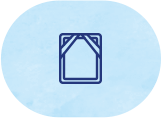

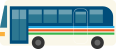


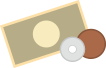











更新日:2025年06月01日