農地を耕作するための売買・貸借(農地法第3条)
農地を売買・貸し借りするには…
農地を耕作目的で売買する場合や、貸し借りをする場合には、農地法による方法と農業経営基盤強化促進法による方法があります。
農地法に基づく売買・貸借
以下の要件をすべて満たす必要があります。
一般要件(売買・貸借ともに適用)
1.全部効率利用要件
農地の権利を取得しようとする者またはその世帯員等が、権利を有している農地および許可申請に係る農地のすべてについて、効率的に利用して耕作の事業を行うと認められること。
2.農地所有適格法人要件
法人が権利を取得する場合には、その法人は農地所有適格法人であること。
3.農作業常時従事要件
農地の権利を取得しようとする者(農地所有適格法人を除く)またはその世帯員が、その取得後において行う耕作に必要な農作業に常時従事(原則年間150日以上)すると認められること。
4.地域との調和要件
取得後において行う耕作の事業の内容および農地の位置・規模からみて、農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生じないこと。
貸借限定の権利移動に係る要件
解除条件付き貸借の要件
農地の貸借に限り、次の要件を満たせば、常時従事要件(個人の場合)、農地所有適格法人要件(法人の場合)を満たす必要がなく、『解除条件付き貸借』として農地の権利(使用貸借または賃借権)を取得できます。
- 貸借契約の中に農地を適正に利用していない場合に貸借を解除する旨の条件が付されていること。
- 地域における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること。
- 法人の場合、業務執行役員のうち1人以上の者が耕作等(企画管理労働等を含む)に常時従事すること。
関連情報
関連情報
農地の賃貸借契約の合意解約通知書類(農地法第3条、農業経営基盤強化促進法)
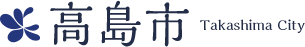











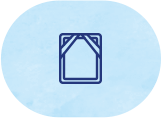

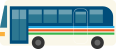


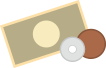











更新日:2025年07月30日