災害による罹災(りさい)証明書等の発行について
罹災証明書・被災証明書とは…
市が発行する、災害による被害の証明書には「罹災証明書」と「被災証明書」の2種類があります。
・「罹災証明書」とは、災害により罹災した”住宅”の「被害の程度」を市が証明するものです。
・「被災証明書」とは、災害により被災した”住宅以外の建物”もしくは”被害が生じた確実な証拠が立証できない住宅”の「被害を受けたことの届出があったこと」を市が証明するものです。
被害認定について
住宅についての「罹災証明書」を発行する場合は、事前に被害認定を行う必要があります。被害認定とは、災害により被災した家屋の被害の程度(全壊、半壊等)を認定することをいい、市により実施します。
〇写真等による自己判定方式について
建物の被害が軽微で、次の条件に合致する場合に、自己判定方式により交付申請をすることができ、市職員による現地調査を省略することができます。これにより比較的早く罹災証明書の交付が可能となります。
1.申請者ご自身で撮影された写真等により被害状況が確認できる
2.被害の程度が「準半壊に至らない(一部損壊)」(=損害割合が10%未満)
3.「準半壊に至らない(一部損壊)」と判定されることに同意している。
被害認定の基準
被害の程度については、国で基準が定められています。住宅の屋根、壁等の経済的被害の全体に占める割合(損害割合)に基づき、被害の程度を認定します。一般的には、次の区分で認定を行います。
|
住宅の損害割合 |
証明される「被害の程度」 |
| 50%以上 | 全壊 |
| 40%以上50%未満 | 大規模半壊 |
| 30%以上40%未満 | 中規模半壊 |
| 20%以上30%未満 | 半壊 |
| 10%以上20%未満 | 準半壊 |
| 10%未満 | 準半壊に至らない(一部損壊) |
証明書の申請手続き
〇罹災証明書等の交付申請には以下の書類が必要です。
・罹災(被災)証明書交付申請書
・被害状況が確認できる写真
・申請される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
・委任状(本人や同一世帯の親族以外が申請される場合)
罹災(被災)証明書交付申請書 (PDFファイル: 434.7KB)
〇申請方法としては以下の方法があります。
・市役所納税課または各支所の窓口にて申請
・郵送での申請
・スマートフォンによる電子申請(申請にはマイナンバーカードが必要です。)
申請期限
災害を受けた日から1年以内に申請してください。
災害を受けてから長期間経過すると、その被害が災害によるものか事実確認が難しくなるため、証明書の交付ができなくなる場合があります。
再調査
交付を受けた罹災証明書について、証明書の内容(被害の程度)について相当な理由をもって修正を求めるときは、再調査の申請をすることができます。
詳しくは市役所納税課までお問い合わせください。
添付資料を見るためには
この記事に関するお問い合わせ先
〒520-1592
滋賀県高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8522
ファックス:0740-25-8103
納税課へのお問い合わせ
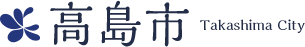











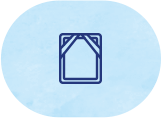

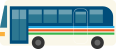


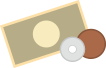











更新日:2025年03月01日