高島市の概要
滋賀県高島市は、琵琶湖の西部に位置し、平成17年1月1日、マキノ町、今津町、朽木村、安曇川町、高島町、新旭町の5町1村が合併し、新市高島市として踏み出しました。
古来より当地域は京都・奈良の都と北陸を結ぶ交通の要衝として栄え、中でも陸上交通は比叡・比良山麓を湖畔に沿って走る西近江路や、塩漬けされた鯖を運搬する街道であったことから鯖街道と呼ばれる若狭街道が主となり、これらの街道と大津方面への湖上交通の拠点である港町や宿場町として栄えてきました。
気候的には、日本海側に近いことから冬季の寒さは厳しく、積雪量の多い日本海側気候となっています。また、秋季には「高島しぐれ」と呼ばれる降雨がしばしばあります。
また、近江聖人と称えられた日本陽明学の始祖、中江藤樹先生生誕の地として知られているとともに、数多くの高島商人(近江商人)を送り出した土地柄でもあります。
首長等
| 市長 | 今城 克啓(いまき かつのぶ) |
|---|---|
| 副市長 | ー |
| 教育長 | 川島 浩之(かわしま ひろゆき) |
人口(令和2年国調)
| 人口 | 世帯数 |
|---|---|
| 46,377 | 18,037 |
| 14歳以下 | 15~64歳 | 65歳以上 | |
|---|---|---|---|
| 年齢構成(人) | 4,959 | 24,449 | 16,648 |
| (構成比) | (10.8) | (53.1) | (36.1) |
| 第1次 | 第2次 | 第3次 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 就業人口(人) | 1,447 | 6,893 | 15,223 | 23,563 |
| (構成比) | (6.1) | (29.3) | (64.6) | (100.0) |
市名の由来
現在の高島市全域の旧郡名で、「高島郡」の名称は、郡という行政区画が成立した奈良時代ころから使われていたと思われます。古くは「万葉集」や「和名抄」などにも登場し、読みは「太加之萬」と記されることから、早い時期から「タカシマ」の呼称が定着していたようです。一説には、三尾国(現在の市南部域と思われる)に高島宮があり、これが高島の名前の起こりになったともいわれています。
名産・特産
- 鮒ずし
- 鯖のなれずし
- ウナギ
- あゆ佃煮
- その他淡水魚の各種加工品
- しいたけ
- 富有柿
- 風車メロン
- 万木かぶら
- 山菜加工品
- とちもち
- 丁稚ようかん
- 高島硯
- 雲平筆
- 高島扇骨
- クレープ製品
- 和ろうそく
- 地酒 など
主な観光名所
- 海津大崎の桜
- メタセコイア並木
- マキノ高原(マキノ)
- 家族旅行村ビラデスト今津
- ザゼンソウ群生地(今津)
- グリーンパーク想い出の森
- 朽木温泉てんくう(朽木)
- 近江聖人中江藤樹記念館(安曇川)
- 針江生水の郷(新旭)
- ガリバー青少年旅行村
- 畑の棚田(高島)
まちづくりの方向
将来目標像
水と緑 人のいきかう 高島市
琵琶湖の水の3分の1を生み出す高島市の自然環境は、永遠に残していきたい高島市の最大の魅力であり、京阪神の生活を支える大切な共有財産。この豊かな自然に抱かれながら、いきいきとした人々の活動や交流による、元気で活発なまちを将来目標像とします。
まちづくり方針
高島の「恵み」と「誇り」を最大化!! ー住みたい、住み続けたいまちの実現ー
社会のあり方が変化する中、高島市の魅力である水と緑を守り、その暮らしから生まれる恵みを大切にしながら、高島市に誇りが持てるまちづくりを進めることにより、高島市の「たからもの」を最大化にして、住みたい、住み続けたいまちの実現をめざします。
庁舎所在地
- 高島市役所本庁舎 (〒520-1592 高島市新旭町北畑565番地)
- 議会事務局
- 政策部
- 総務部
- 市民生活部
- 環境部
- 健康福祉部
- 子ども未来部
- 農林水産部
- 商工観光部
- 都市整備部
- 会計課
- 教育委員会事務局
- 選挙管理委員会事務局
- 監査委員事務局
- 公平委員会事務局
- 農業委員会事務局
- マキノ支所 (〒520-1892 高島市マキノ町沢1410番地)
- 今津支所 (〒520-1692 高島市今津町弘川204番地1)
- 朽木支所 (〒520-1492 高島市朽木市場604番地)
- 安曇川支所 (〒520-1292 高島市安曇川町田中89番地)
- 高島支所 (〒520-1192 高島市勝野215番地)
この記事に関するお問い合わせ先
〒520-1592
滋賀県高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8130
ファックス:0740-25-8101
企画広報課へのお問い合わせ
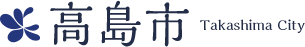











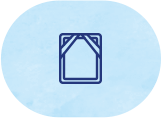

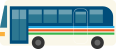


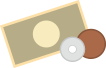











更新日:2025年02月13日