中江藤樹

どんなひと?
1608(慶長13年)-1648(慶安元年)。江戸時代初期の儒学者。わが国における陽明学の開祖。数多くの徳行、感化によって、没後に《近江聖人》とたたえられる。近江国高島郡小川村(現在の滋賀県高島郡安曇川町上小川)に、中江吉次の長男として生まれる。
名は原(げん)、字は惟命(これなが)、号は嘸軒または顧軒、通称は与右衞門(よえもん)、幼名は原蔵(げんぞう)という。普通おこなわれている藤樹とは号でなく、屋敷に生えていたフジの老樹から、門人たちが《藤樹先生》と呼んだ尊称に由来する。
9歳、米子藩主加藤貞泰の家臣であった祖父・中江吉長の養子となり、米子に行く。10歳、藩主の国替えにともない、伊予国大洲(現在の愛媛県大洲市)に移り住む。15歳、祖父の死去により、100石取りの武士となる。17歳、独学で『四書大全』を読み、朱子学に傾倒する。しかし、33歳のとき、『王龍渓語録』を、37歳のときには『王陽明全書』を入手するや、熟読玩味して、おおいに触発感得をうける。それまでの学問上の疑念が解け、格法主義的な生活の非なることを知り、しだいに王陽明の「致良知説」へと信奉していった。これより以前の27歳のとき、母への孝養と自身の健康を理由に大洲藩士の辞職を佃家老に願いでるが、ついに許可を待たずに脱藩して、ふるさとの小川村へ帰る。浪人(牢人とも書く)となった藤樹は、居宅を私塾として開き、41歳で亡くなるまでのおよそ14年間、大洲からやってきた藩士や近郷の人々に《孔孟の学》や《陰隲》を教導する。
代表的な門人としては、熊沢蕃山、淵岡山、中川貞良・謙叔兄弟、泉仲愛らがいるが、とりわけ藤樹没後における蕃山の事績によって、藤樹の名声をいちだんと高めたことは注目しなければならない。
また、魯鈍の門人であった大野了佐にたいして、大部の『捷径医筌』を著わし、それをテキストにして熱心に医学を教え、立派な一人前の医者に育てあげた話は、人を教えて倦まない藤樹の生き方を知るうえで、あまりにも有名なエピソードの一つである。
藤樹の著書は、『藤樹先生全集』全5冊(岩波書店版、昭和15年)に収められている。そのおもなものとして、『翁問答』『鑑草』『孝経啓蒙』『論語郷党啓蒙翼伝』『論語解』『大学考』『大学解』『大学蒙註』『中庸解』などがある。
藤樹先生に学ぶ
藤樹先生の字(あざな)
藤樹書院の祭壇中央に祀られている先生の神主〔仏教でいう位牌にあたります〕の陥中(かんちゅう)に、小さな文字で「与右衞門公、姓中江、諱原(げん)、字惟命(これなが)、大宗神主」と墨書されています。これによって≪中江与右衞門惟命≫が、先生の元服以後における武士としての正式な名前であったことがわかります。普通行われている中江藤樹は、後世の学者・文人が便宜上つけた呼称であり、その藤樹とは門人たちが誰いうとなく「藤樹先生」と尊称したことに由来するのです。江戸中期のベストセラーとなった橘南谿の『東遊記』には、「藤樹先生」という項目のなかで藤樹書院を訪れた際の記事が載せられています。
ところで、諱(いみな)とは死者の本名、つまり生存中の「名」にたいし死んでからは「諱」となり、したがって「名は原」ともいえるわけです。先生9歳のとき、わずか1年だけ住んでいた伯耆(鳥取県)の米子では、先生の幼名を《原蔵》と呼んでいたことが、今に伝わっています。のちの先生の執筆された漢詩などの著作の末尾には、「中江原」もしくは「中江原拙稿」と署名されています。また、先生の門人に宛てた書簡には、「中江与右衞門(よえもん)」とし、その下には花押があります。
字は、元服の際、実名のほかにつける名のことで、ふだん武士連中は人の名を言わずに、字で呼びあうのが礼儀でありました。おそらく先生は、大洲藩の同僚から、「惟命どの」などと呼ばれていたのでしょう。先生が元服されたのは、祖父・吉長が亡くなった同じ年の15歳で、もちろん伊予の大洲においてでありました。
さて、先生の祖父の字は、《吉長》、父親は《吉次》、叔父は《吉久》と呼ばれていましたので、先生もまた、《吉◯》と名乗るのが当然だったように思います。けれどもそうでなく、《惟命》という大変難解な字でありました。いったい、誰がそれの名付け親だったのでしょうか。まず考えられるのは、近江の小川村に住んでいた父親です。しかし、先生は9歳のときから、祖父の養子として育てられることになりましたので、先生と一緒に暮らしていた祖父が名付け親だったといえます。とはいうものの、75歳の祖父は、まさしく戦国時代に生きたいくさ一筋の武士ゆえに、このような難しい字をつけるほどの知識はほとんどなかったように思われます。
この惟命が何にもとづいて命名されたのか、今では推測の域を出ませんが、たとえば『大学』に「(書経の)康誥に曰く、惟れ命つねにおいてせず」とあり、また『春秋左氏伝』にも「惟だ命をこれ聴く」とあります。ここでの命とは、天命にほかなりません。このような古代中国の経書のなかから、字がつけられたということが考えられます。
この当時の大洲において、これほどの豊かな教養をそなえた人物はというと、たった一人しかおりません。すなわち、大洲藩主加藤侯の菩提寺、曹渓院の臨済僧・天梁和尚(てんりょうおしょう)です。はたして、先生の元服する前年の14歳のときには、その和尚から手跡、詩および聯句などを学んでいたのです。
祖父と藩祖
祖父と藩祖 《近江聖人》とたたえられ、また《日本陽明学の開祖〉として歴史に名をとどめるほどの偉人が湖西の地から、どうして輩出したのかこれが私たちの藤樹先生に向けられる最大の関心事といえます。それと併せて、先生のような人格がいったいどのようにして形成され、誰の影響を深くうけたのか、この点も興味をいだかせる話題であります。
『藤樹先生年譜』によると、九歳の時、はじめて文字の読み書きを習い、一年ほどで祖父の書簡を代筆するまでに習得、十歳の時には庭訓住釆や貞永式目をも学び、習えばそれらを一字として忘れることがなかったといいますから、少年時代からきわめて明断な頭脳の持ち主であったことがうかがえます。
そのため祖父は人に違うごとに、孫のかしこさをすいぶん自慢していたほどです。さらに十七歳の時、中国輸入の句読点のない『四書大全』を独学して理解できたというのですから、その秀才ぶりをもわかります。そのような少年時代の先生に深く影響を与えたのは、やはり祖父・吉長だったと思われます。
先生十二歳のある時、毎日こうして食事ができるのは誰の恩か。それは《両親》と〈祖父》と《君》の三つ恩だと。これよりこの恩を忘れてはならない、ということが「年譜」に載っています。
この《君》とはもちろん大洲藩主加藤貞泰にあたりますが、この場合はそうでなく藩祖加藤光泰をさします。もともと祖父は小川村で農業を営んでいたのですが、加藤光泰が高島城主となった頃、三十歳のなかばで仕官し武士となりました。ところで藩祖光泰は美濃の地侍でしたが、最初織田信長に仕え、さらに豊臣秀吉に仕えてはめざましい戦功をあげ、甲斐国二十四万石の大名にまで出世しました。ところが、文禄の役で朝鮮へ渡り、戦地で病没したのです。光泰は最初のいくさの折、歩行が困難となるほどの重傷をおったのですが、わが一族繁栄のために一所懸命の武士でした。
祖父が百石取りの武士として生活できるのも、また大洲藩が今日あるのも、それはすべて生命を賭して生きた藩祖光泰のおかげであったわけです。もちろん先生にしますと、藩祖の顔も知りませんでしたが、おそらく祖父はいつも先生に藩祖の人柄やいくさの苦労話を語っていたものと思われます。この三つの恩のように、先生は物事の背後にある本質を見抜く哲学的思考が早くから人一倍強かったのでしょう。
早羅山への挑戦
大洲在藩時代の先生は、郡奉行としての役目に精励するいっぽう、幕府お抱え儒者の林羅山および林家やそれに追従する儒者の動向に対して、深い関心をはらっていました。
先生二十二歳の冬、京都の友人から一通の書簡が届き、その書尾に、林羅山の長子・叔勝の著わした「安昌、玄同を弑(しい)するの論」が写されていました。それを読んで、先生は非常に辛らつな短篇論文を翌年に書き上げたのです。
寛永五年、先生二十一歳の時、祇園祭の夜に儒者・菅玄同(かんげんどう)が弟子の安田安昌(やすだあんしょう)に刺殺されるという事件が起きました。林叔勝は、菅玄同は立派な儒者だと持ち上げ、殺害におよんだ玄同の弟子安昌を批難したのです。それに対して先生は、玄同・安昌ともに「これ人面獣心の俗なり」として林叔勝の考えを厳しく批判したわけです。その根拠を先生は「孟子(もうし)」のなかに求めました。
ぼ-盆成括(ぼんせいかつ)という人物が斉の国に仕えた。孟子は「死んでしまうぞ、あの男は」と。門人がその理由を尋ねると「彼の人柄は小にして才があり、いまだ君子の踏むべき道を聞いていない。これだけの条件がそろえば、殺されても仕方ない」と孟子は答えた。
藤原惺窩(ふじわらせいか)の門人として京都では名の知られた玄同の、これまでの言動について先生はいろいろな風聞を耳にしていたのでありましょう。玄同なる人物は、ただ博識をほまれ湯島聖堂(東京)とし、その中味たるや己の才能にたよる、だけの〈口耳(こうじ)の学問〉であって、徳を知らない。そのため玄同が弟子の安昌を待つ態度は、あたかも犬や豚のようであった。それゆえ安昌が常軌をいっして、殺人におよんだのは当然であったろう、と。
先生は、儒者には《真儒(しんじゅ)》と《俗儒(ぞくじゅ)》の二種類があるといいます。玄同や安昌などは、まさしく後者の典型とみました。古代中国の聖賢の教えに学んで、まず自分自身を立派に修養し、そして《善》の政治をおこなうのが《真儒》。先生は、これこそがあるべき儒者の姿だと考えました。先生二十四歳の時には、「林氏、髪を剃(そ)り位を受くるの弁」という論文を書きあげ、今度は三代将軍家光のブレーン林羅山の言行を痛烈に批判しました。先生の眼からみれば、羅山といえども《俗儒》に過ぎないのです。勿論羅山には、先生のことなど知るよしもありません。大洲で著わされたこの二篇の論文は、先生にとって以後の人生を決定づける宣言書ともいえるのです。
大橋家老のこと
大洲在藩時代の先生を語るうえで、大橋家老(おおはしかろう)についてどうしてもふれておく必要があります。『藤樹先生年譜(ねんぷ)』元和七年、先生十四歳の条に次のような記述がのっています。
ある時、家老の大橋氏が四、五人の同僚をともない祖父・吉長の屋敷にやって来て、夜遅くまで座談をした。そこで先生は、家老という重職のある人ならば藩政のことなど、きっと常人とは異なった重要な話をされ、学ぶべきものがあるに違いないと思い、壁を隔てて隣の部屋からじっと聞いていた。けれども、それはただの世間話に終始したとみえて、「何の取り用ゆべきことなし。先生ついに心に疑ひてこれを怪しむ」と。
このような逸話から、つとに大橋家老はあまり大した人物ではなかったとみなされてきましたが、この見方は字ずらの理解であって、間違っています。むしろ、先生にとって大橋家老は《命の恩人》といっても過言ではないのです。
その間違っている理由をのべる前に、大橋家老について簡単にふれておきましょう。
正しくは大橋作右衛門重之(さくうえもんしげゆさ)といい、千八百石の禄をはみ、加藤外記(藩主の分家)につぐ家老ですが、実質的には六万石の藩政をあずかるほどの首席家老であったと思われます。というのは、作左衛門の祖父・長兵衛は、最初秀吉の家臣でしたが、元亀(げんき)二年の湖北小谷城(おだにじょう)攻めの頃に藩祖・加藤光泰の家老となり、それ以来、大橋家は光泰、貞泰の一一代、動乱の半世紀にわたり、藩主と苦楽をともに分から合ってきた家筋なのです。
さて、前述の理由の第一として、「藤樹先生年譜』は先生の履歴をつづったのでなく、思想形成の遍歴を重点に編まれたものです。したがって先大洲城の櫓(重要文化財)生十四歳の条の言動というのは、いわば先生の儒教的理想主義の発露とみなすべきでしょう。大橋家老がわざわざ百五十石取の七十四歳の祖父の屋敷に足を運び、しかも雑談に終始したところに、藩の最高責任者としてのろうかいな人事掌握ぶりがうかがえるのです。十四歳の先生には、政治のことまで見抜くことは無理かも知れません。
第二には、先生晩年のころと思われる大橋家老あての書簡一通が残されており、そのなかに家老から先生に高価な「あやぬの」を贈られたことへのお礼の言葉がのっています。先生は許可なく大洲藩を脱藩したとはいうものの、大橋家老と先生との間には、じつはあつい信頼関係で結ばれていたのです。
蕃山の弟・泉仲愛
藤樹先生の門下には、大洲の中川貞良、謙叔といった兄弟がいましたが、もうひと組の兄弟門人もいました。有名な熊沢蕃山(くまざわばんざん)とその実弟の泉仲愛です。この泉仲愛もまた、先生の代表的門人として、けっして忘れてはならない人物の一人であり、少しく取り上げてみましょう。泉仲愛、通称は八右衛門(はちえもん)といい・元和九年・野尻一利(のじりかずとし)の次男として生れ、十四歳のときに、平戸(ひらど)藩士岩田治左衛門(いわたじざえもん)の養子に入りますが、二十歳のとき、わけあって牢人(ろうにん)の身となります。その二年後の正保元年に、仲愛は小川村へやって来るのです。「藤樹先生年譜」先生三十七歳の条(くだり)に、「秋八月、岩田長(いわたちょう)、来(きた)りて業(ぎょう)を受(う)くとあります。このように、仲愛が一代決心して牢人となった理由について、などて詳しくは知り得ませんが、ただその前年の冬、兄の蕃山が念願の先生の門にまなび、翌年の四月まで、《良知心学》の神髄(しんずい)を体認(たいにん)せられたこと、その蓄山が仲愛にたいして、学問の必要をすこぷる熱心に伝えたと推測しても、過言ではないものと思われます。藤樹書院での仲愛は、中川謙叔らとともに、先生のもとで一段と《良知心学》の研さんを深めていくのでずが、先生が没して二年後の慶安三年の春、兄の推挙によって、備前岡山藩(びぜんおかやまはん)の武士として召し抱えられ、八年におよぶ困窮の牢人生活から脱することになります。ときに仲愛二十八歳でした。以後、仲愛は、近習(きんじゅう)・足軽頭(あしがるがしら)・学校奉行(がっこうぶぎょう)などの役職を歴任するのですが、わけても八十歳で亡くなる二年前までの、およそ三十数年にわたって、岡山藩の教育行政の最高責任者にあたる学校奉行という重職に就いていたことは、注目すべきです。《藤樹学》が岡山の地におよんだのは、蕃山の功績はもちろんのことですが、実務派・仲愛の事跡も看過できません。名君池田光政(いけだみつまさ)が死の床にあるとき、仲愛は末座につらなり、遺言も聞かれたということからしても、岡山藩内における仲愛の立場がわかります。
最後に、仲愛の逸話をひとつ。
-岡山領内の兄弟か田地の相続をめぐって喧嘩(けんか)をし、互いに党援(とうえん)かできて、代官の命にも従おうとはしません。光政侯は、その仲裁を仲愛に命じました。そこで仲愛は兄弟を屋敷に呼びつけて、小さな一室に入れて置き、家臣が『主人は急な所用ができたので、しばらく待つように。食事と風呂は自由に取っても結構です」という仲愛の言葉を伝え、仲愛は終日会おうとはしませんでした。その間、兄弟はいかみ合って、何も語し合おうとはしません。けれど段々と幼い頃のことや、両親に大切に育てられたことを思い出すと、ついには兄弟涙を流して、互いに自分の非を詫(わ)び、そこへ仲愛が部屋に入り、一言『本当に喜ばしいこと』と話し、兄弟は家へもどったのです。
遺品のあれこれ
正直馬子
ある日、河原市(現在の滋賀県新旭町安井川)に住む馬子の又左衞門は、京都へのぼる加賀の飛脚を馬に乗せました。そして、仕事を終えて河原市にもどり、馬を洗おうと鞍を取り外すと、さいふのような袋が出てきました。その中味を改めると、なんと金子200両もの大金が入っているのでした。
驚いた馬子は、「これはもしかしたら、さっきの飛脚のものかも知れない。今ごろは、あの飛脚きっと困り果てているに違いない」と思うと、ふたたび馬子は日暮れの道をとって返し、飛脚の泊まっている榎の宿(現在の滋賀県志賀町和邇)まで、30キロの道のりを走っていったのです。
いっぽう、飛脚はというと、旅篭で旅の疲れをいやそうとしたところ、大金の入った袋が手元にないことにようやく気づき、必死であたりを捜したものの、どこにも見つかりませんでした。
そうした折、馬子が旅篭に現われたのです。飛脚に会って、いろいろ仔細をたずねると、確かに飛脚の置き忘れ物であることがわかり、馬子は200両の入った袋をそっくりそのまま返してあげたのです。
「この金子は藩の公金で、京の屋敷へ送り届けるためのものです。もしも、この金子200両が見つからなかったときは、自分の命は申すまでもなく、親兄弟までもその累がおよんで、重い罪になるところでした」と、飛脚は涙ながしながら話すのでした。
そこで飛脚は、行李より別の金子を取り出し、当座のお礼として馬子に15両を差し上げるのですが、馬子は一向それを受け取ろうとはしませんでした。馬子は、「そなたの金を、そなたに返したただけなのに、なんでお礼などいりましょうや」と言うばかり。そこで、飛脚は10両と減らし、5両、3両と減らして馬子に受け取ってもらおうとするのですが、それも受け取ろうとはしません。困りはてた飛脚の顔を見かねて、ようやく馬子は「それじゃ、ここまで歩いてきた駄賃として鳥目200文だけは頂戴いたしましょう」と。
200文を受け取った馬子は、その金で酒を買ってきて、旅篭の人たちと一緒に酒を飲み交わしました。酒もなくなり、ほろ酔い機嫌で馬子が帰ろうとすると、飛脚は感激のあまり「あなたはどのような方か」と問うのです。
馬子は、「自分はこのように名もない馬子に過ぎません。ただ、自分の在所の近所に小川村(現在の滋賀県安曇川町上小川)というところがあって、この村に住んでおられる中江与右衞門(藤樹)という先生が、毎晩のように講釈をしておられ、自分も時々は聞きにいくのです。先生は、親には孝を尽くすこと、人の物を盗んではならないこと、人を傷つけたり、人に迷惑をかけてはならないことなど、いつも話されておられます。今日の金子も、自分の物ではないので、取るべき理由がないと思ったまでのことです」と言って、夜遅くふけて河原市へもどりました。
問い合わせ先
中江藤樹記念館・たかしまミュージアム
電話 0740-32-0330












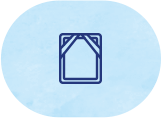

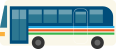


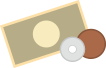











更新日:2025年06月03日