空家の適正な管理をお願いします!
空家をお持ちでお悩みの方
家は、住まなくなるとあっという間に老朽化が進みます。適正に管理をしなければ、建物の倒壊や敷地内の草木の繁茂、不審者の侵入、動物の棲み処になるなど、保安上の危険や衛生面においても近隣住民の生活に及ぼす影響は深刻です。空家をお持ちの方は、定期的に管理を行い、外壁等の破損や倒壊の危険がある場合は、修繕や解体、敷地内の除草や樹木の剪定を行いましょう。
老朽化が進む前に、空家を利活用したい(売却や賃貸)とお考えの方、
「空き家紹介システム」 をご存知ですか?
詳しくはこちら↓
毎月第3土曜日に空き家活用相談会を開催しています!
老朽化した空家は、倒壊や瓦の飛散等による周囲への危険を防ぐためにも、早期に除却(解体)を進めることが大切です。
実際に空家の除却(解体)は、どのような流れで進めたらよいのか?
滋賀県ホームページ 空家の除却(解体)の進め方はこちら↓
【空き家の解体・売却で迷っている方へ】滋賀県版「すまいの終活ナビ」をご利用ください!
老朽化した空家の解体費用をシミュレーションすることができます!
近隣の空家でお悩みの方
近隣の空家については、当事者間で対応していただくことが原則ですが、市民協働課では、適正に管理をされていない空家のご相談を受付けています。
電話の場合は、0740-25-8526 へご連絡ください。
注)適正に管理されていない空地に関するご相談は、環境政策課(0740-25-8123)へお願いします。
ご相談される際は、次のことをお伝えください。
・相談される方の氏名、連絡先
・空家の場所
・空家の状況
・空家の状態がどのくらい続いているか
空家とは、1年以上利用されていない建物です。最近空家になった、別荘として使われている、居住されている家屋に関するご相談には対応できません。
空家に関するご相談をお受けした場合は、法や条例に基づき、情報提供等を文書にて行いますが、所有者等の調査には、時間を要します。
市では、草木の伐採やハチの巣の駆除、修繕や解体等の対応はできません。また、市から送付する文書は情報提供であり、対応を強制することはできません。
注)空家等対策の推進に関する特別措置法第22条に基づく措置(特定空家等への勧告・命令)及び行政代執行については、空家を放置することが著しく危険な状態等(公道への倒壊による人身への危険がある場合)で、特定空き家等に認定された空き家に限り行うものです。
「越境した竹木の枝の切取り」について令和3年、民法改正によりルールが改正されました。
越境された土地の所有者は、竹木の所有者に枝を切除させる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができるようなりました。(新民法233第3項)
1竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
2竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
3急迫の事情があるとき
越境した木の枝の切り取りを考えられた場合は、事前に弁護士や司法書士等の専門家へご相談ください。市では、越境した竹木の枝を法的に切除可能か、費用の請求が可能かどうかについては、判断はできません。
法律上の問題の解決については、事前に専門家への相談をお勧めします。
・滋賀弁護士会 077-522-3238
・滋賀県司法書士会 077-525-1093
よくある問い合わせ
Q 空家の所有者の情報を教えてもらえますか。
A 所有者に関する情報等、個人情報はお伝えすることはできません。
Q 空家の草が越境してきているのですが、市で刈ってもらえますか。
A 空家の所有者等において管理責任があるため、市では、空家の敷地の草を刈ることはできません。
Q 空家の所有者を調べるのはどうすればよいですか。
A 法務局で登記事項証明書の交付や閲覧をすることができます。(有料)
Q 空家に蜂の巣ができて困っているのですが、市で駆除してもらえますか。
A 駆除は、空家(敷地内を含む)の所有者が行うことになります。市では、蜂の巣の駆除はできません。
Q 越境した枝の切り取りについて、催告してから相当期間内とはどのくらい待てばいいですか。
A 所有者に枝を切除するために時間的猶予を与える趣旨で、2週間程度と考えられています。
<ご参考>
民法(抜粋)(土地の工作物等の占用者及び所有者の責任)
第717条土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2前項の規定は、竹木の植栽又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3前2項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占用者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
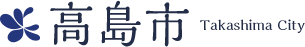











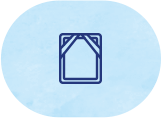

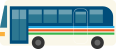


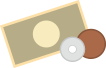











更新日:2025年10月16日